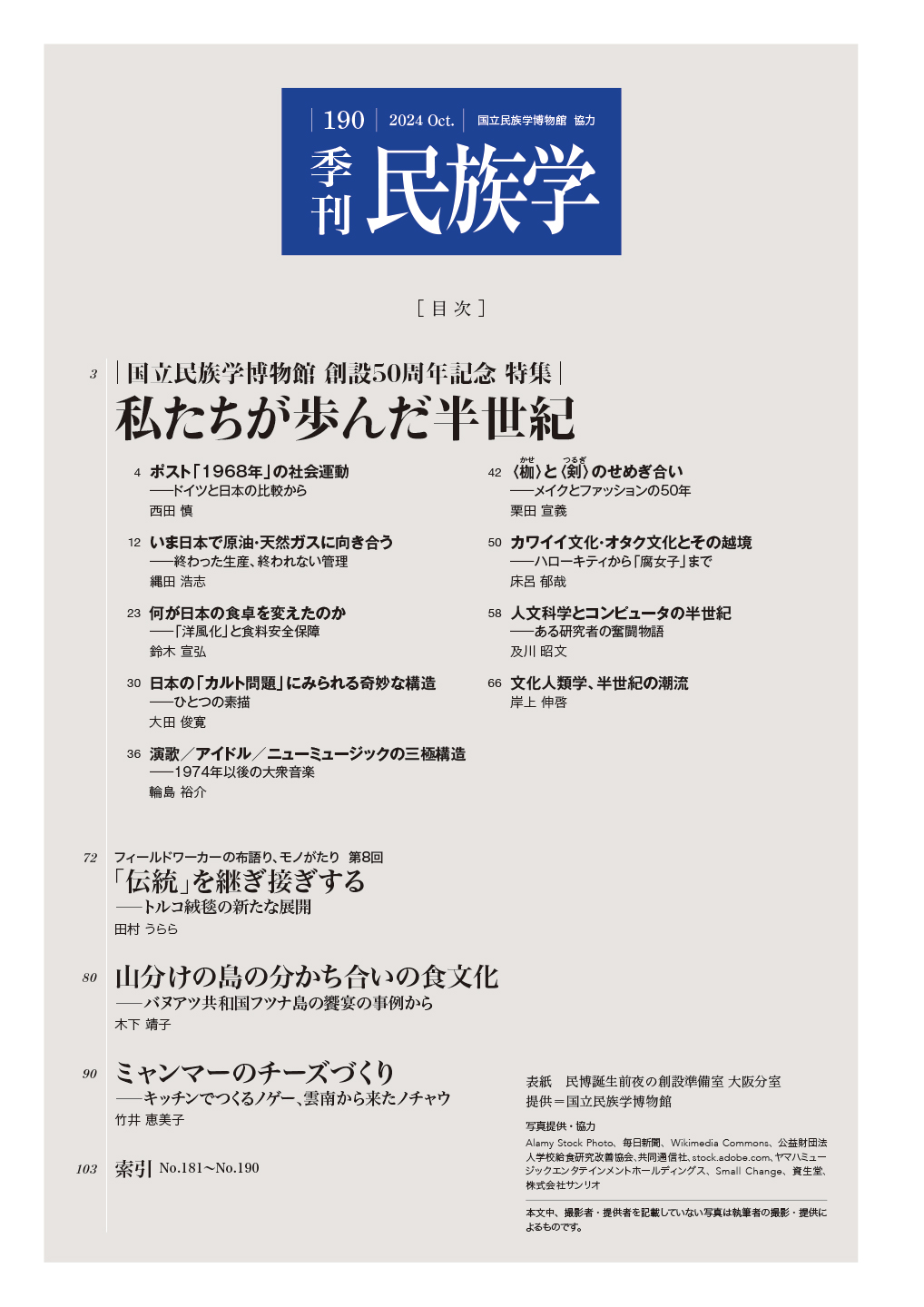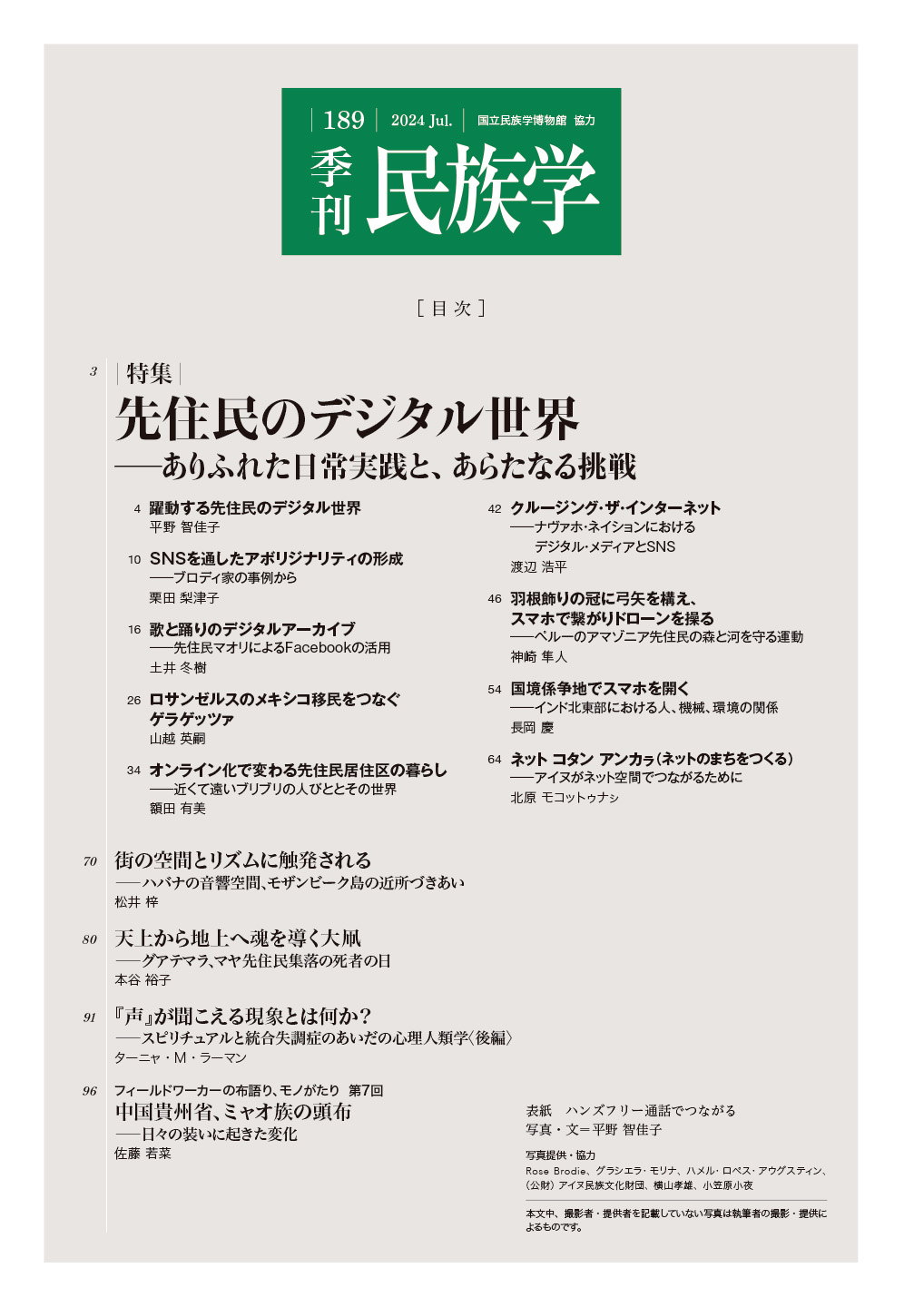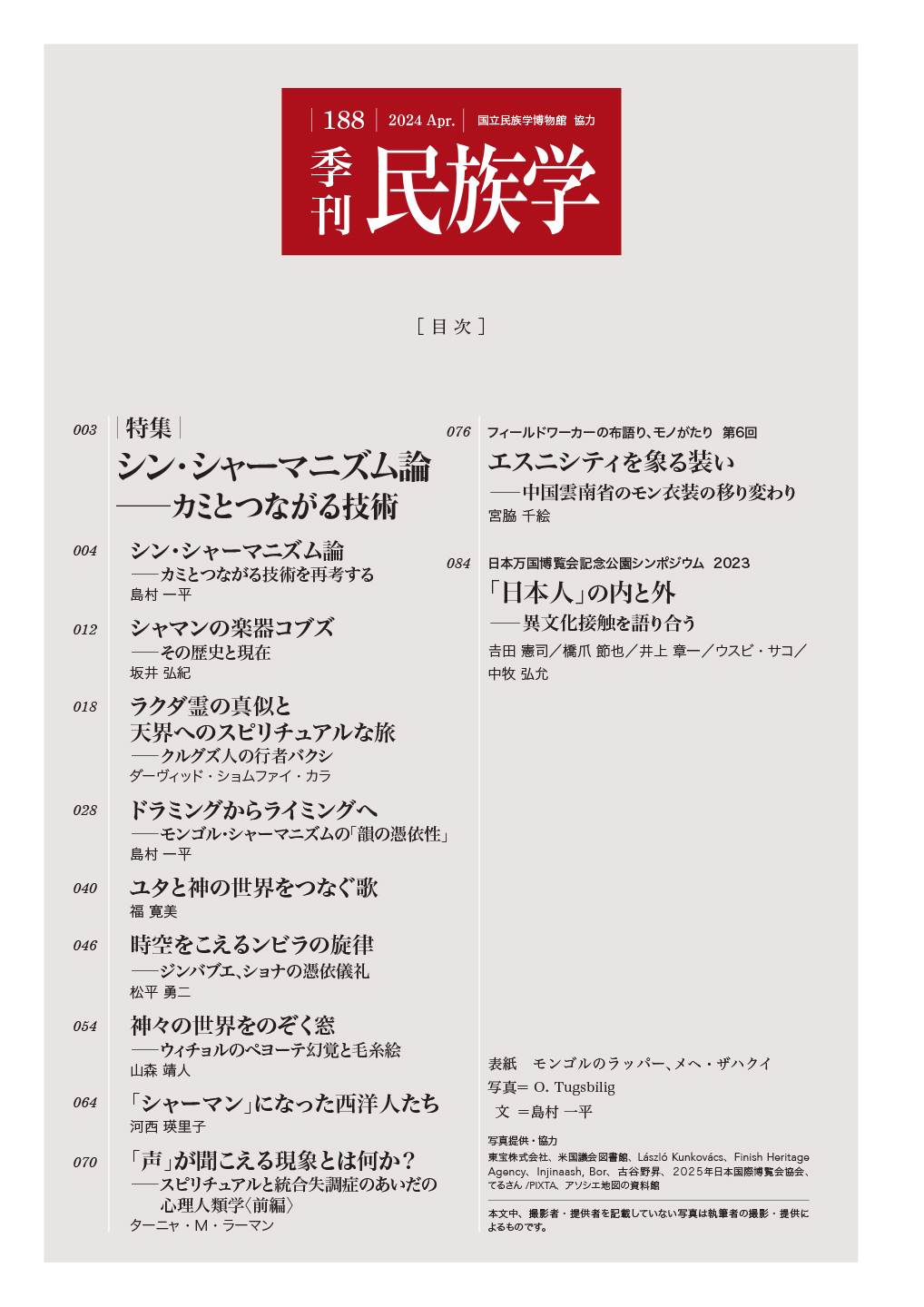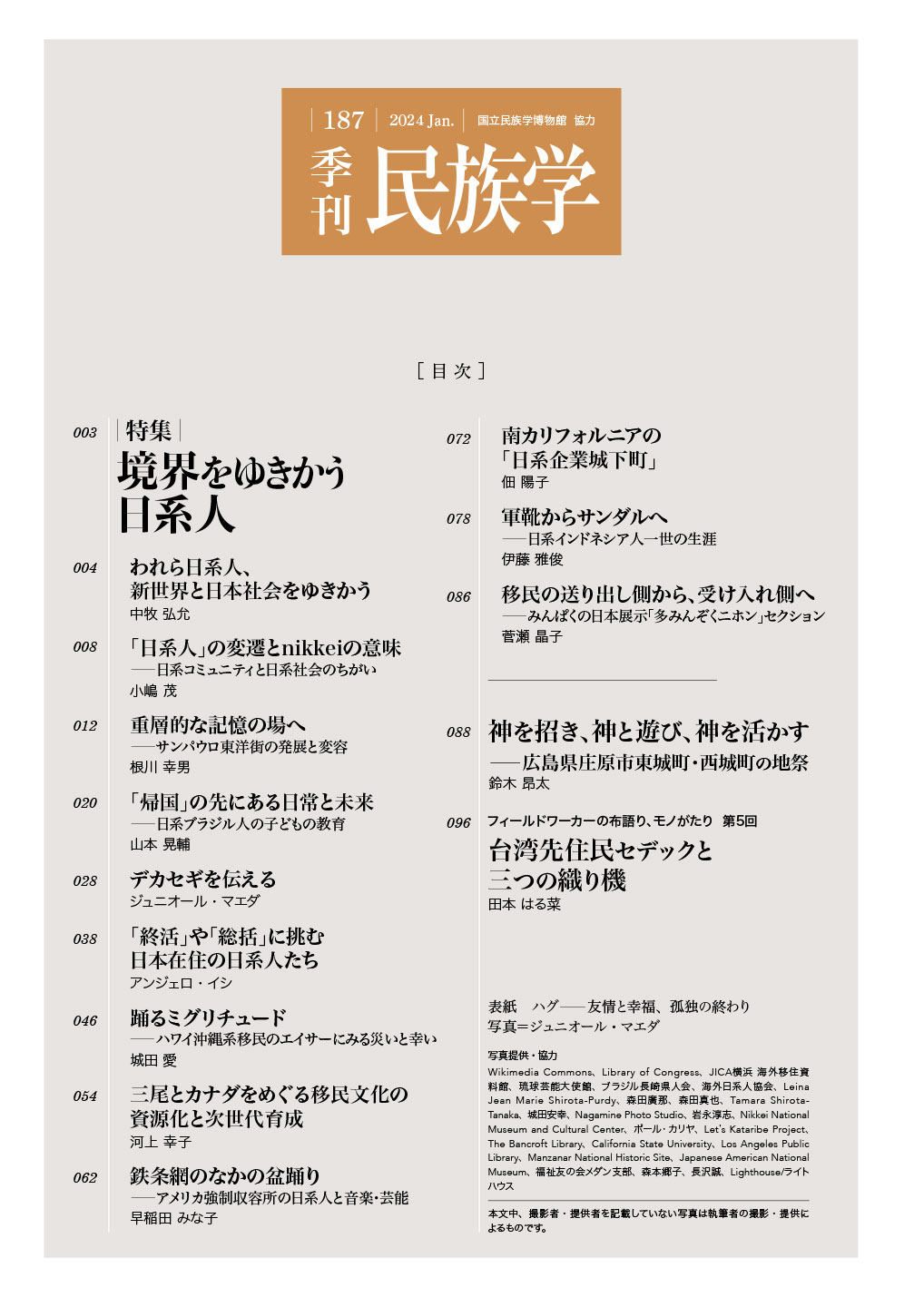国立民族学博物館 創設50周年記念 特集 私たちが歩んだ半世紀
1960年代の世界を彩ったのは「異議申し立て」だった。近代的価値観、科学技術万能主義、進歩史観、成長神話や中央集権的価値観から決別し、さまざまな分野で新たな道を模索する動きがはじまった世界史的な一大画期だったといえる。国立民族学博物館が創設された1974年は第一次オイルショックを機にそれらの動きが一転し、別のモードへの移行が始まる年でもあった。 一般に歴史年表は、縦軸に年を、横軸に政治、経済、社会、文化、世相などのテーマを配することが多い。バタフライ効果ではないが、テーマごとの縦長年表を横方向にまたがってつなぐ相関関係を見出すことが、歴史年表を読む醍醐味のひとつに相違ない。本特集も、いくつかのテーマを横軸に置いて年表を思い描いてみるとどうなるか、の試みである。読者諸賢はこの50年を振り返るなかで、本特集の論考で暗示されている諸々の相関関係への洞察をお持ちになるにちがいない。そうした洞察が、次の、より良い時代への展望につながることを、願わずにはいられない。
- 000 表紙「民博誕生前夜の創設準備室 大阪分室」提供:国立民族学博物館
- 001 目次
- 002 表紙のことば 文:編集部
- 003 国立民族学博物館 創設50周年記念 特集「私たちが歩んだ半世紀」
- 004「ポスト『1968年』の社会運動――ドイツと日本の比較から」西田 慎(奈良教育大学教授)
- 012「いま日本で原油・天然ガスに向き合う――終わった生産、終われない管理」縄田 浩志(京都大学教授・国立民族学博物館客員教授)
- 023「何が日本の食卓を変えたのか――『洋風化』と食料安全保障」鈴木 宣弘(東京大学大学院特任教授)
- 030「日本の『カルト問題』に見られる奇妙な構造――ひとつの素描」大田 俊寛(埼玉大学非常勤講師)
- 036「演歌/アイドル/ニューミュージックの三極構造――1974年以後の大衆音楽」輪島 裕介(大阪大学教授)
- 042「〈枷(かせ)〉と〈剣(つるぎ)〉のせめぎあい――メイクとファッションの50年」栗田 宣義(甲南大学教授)
- 050「カワイイ文化・オタク文化とその越境――ハローキティから『腐女子』まで」床呂 郁哉(東京外国語大学教授)
- 058「人文科学とコンピュータの半世紀――ある研究者の奮闘物語」及川 昭文(総合研究大学院大学名誉教授)
- 066「文化人類学、半世紀の潮流」岸上 伸啓(国立民族学博物館名誉教授)
- 072 連載 フィールドワーカーの布語り、モノがたり 第8回
「『伝統』を継ぎ接ぎする――トルコ絨毯の新たな展開」田村 うらら(金沢大学准教授) - 080「山分けの島の分かち合いの食文化――バヌアツ共和国フツナ島の饗宴の事例から」木下 靖子(沖縄美ら島財団総合研究所研究員)
- 090「ミャンマーのチーズづくり――キッチンでつくるノゲー、雲南から来たノチャウ」竹井 恵美子(大阪学院大学教授)
- 103 索引索引 No.181〜No.190
「トラつば」ロスからタイトルバックの群舞や胸熱シーンを振り返って涙ぐむ私を老人性感情失禁と細君は笑いますが、NHKの朝ドラ「虎に翼」から現代史の見方を多々教えられました。
近代的歴史の見方が生まれた一九世紀欧州は科学の世紀、自然科学に負けじと客観性を求め、記憶を排除し公的記録に依拠する実証主義から始まった近代歴史学は、その後、時代の雰囲気や状況によって変化してきたそうです。国民国家形成に資する歴史学、その欺瞞的客観性への批判、対象を民衆や周縁領域に広げる動き、言語の恣意性に依存する記録より民衆記憶や語りの重視、専門家任せではない歴史学の模索、グローバリズムさらには地球史も含めたビッグ・ヒストリーなど。つまり歴史学自体も、政治・経済、文化や思想に影響され続けてきた、歴史的な事象なのですね。
歴史学を、膨大な「真実」の事象群から取捨選択した「事実」の間の因果関係を解釈する営み、と言うなら百人百様の歴史観があって当然、特に現代史の場合、事象に遭遇した当事者には自己弁護や正当化のバイアスがかかるので、むしろ後の世代の方がより客観的で俯瞰的見方になる、との論があります。
また事象の同時代人でも、事態の進行中に全体像をつかむのはかえって困難、団塊世代の私も異議申し立てが世界史上の画期とは、後で知りました。本特集の場合、執筆者のほとんどは団塊の次の世代ですが、育った時代の政治・経済・文化環境の違いが歴史観にも微妙な違いを生んでいるようにも思います。
歴史から学ぶことは可能でしょうか。自然科学は再現性を重視するが、人間社会の事象は一回性なので歴史学は科学ではなく教訓は得られぬとの見方があります。が、自然科学でも、原子レベルまで同一の条件下での再現は不可能であり確率論的な因果関係を問うのだから、歴史学でも条件を整えれば因果推論が可能で教訓を導くことはできるとの議論もあります。
冷戦終結後、民族主義や自国中心主義がかえって強まり、弱者ばかり苦しむ紛争や分断が蔓延しています。衣食足りて礼節を知る、ではないが、貧困と差別がなくなれば世界は平和になるかも知れません。が、それとはほど遠い現状、人類は歴史から何も学ばなかったか、と悲観的になります。「トラつば」の主題歌ではないけれど、100年先に、前半50年の教訓を踏まえ、貧困・差別のない穏やかな未来が来るのを願います。
(編集長 久保正敏)
2024(令和六)年10月31日発行
発行所:公益財団法人 千里文化財団
「国立民族学博物館友の会」へご入会いただければ定期的にお届けいたします。