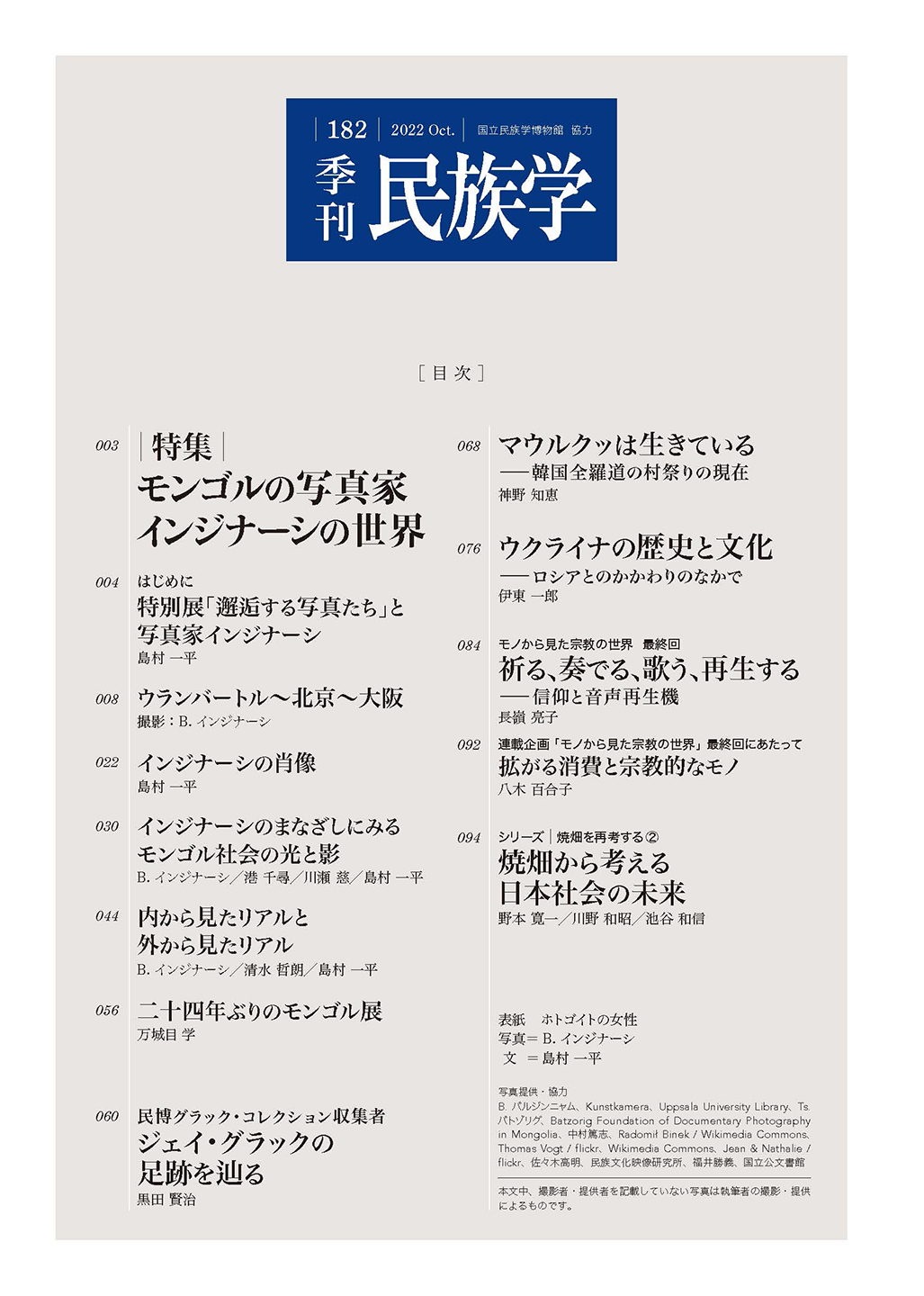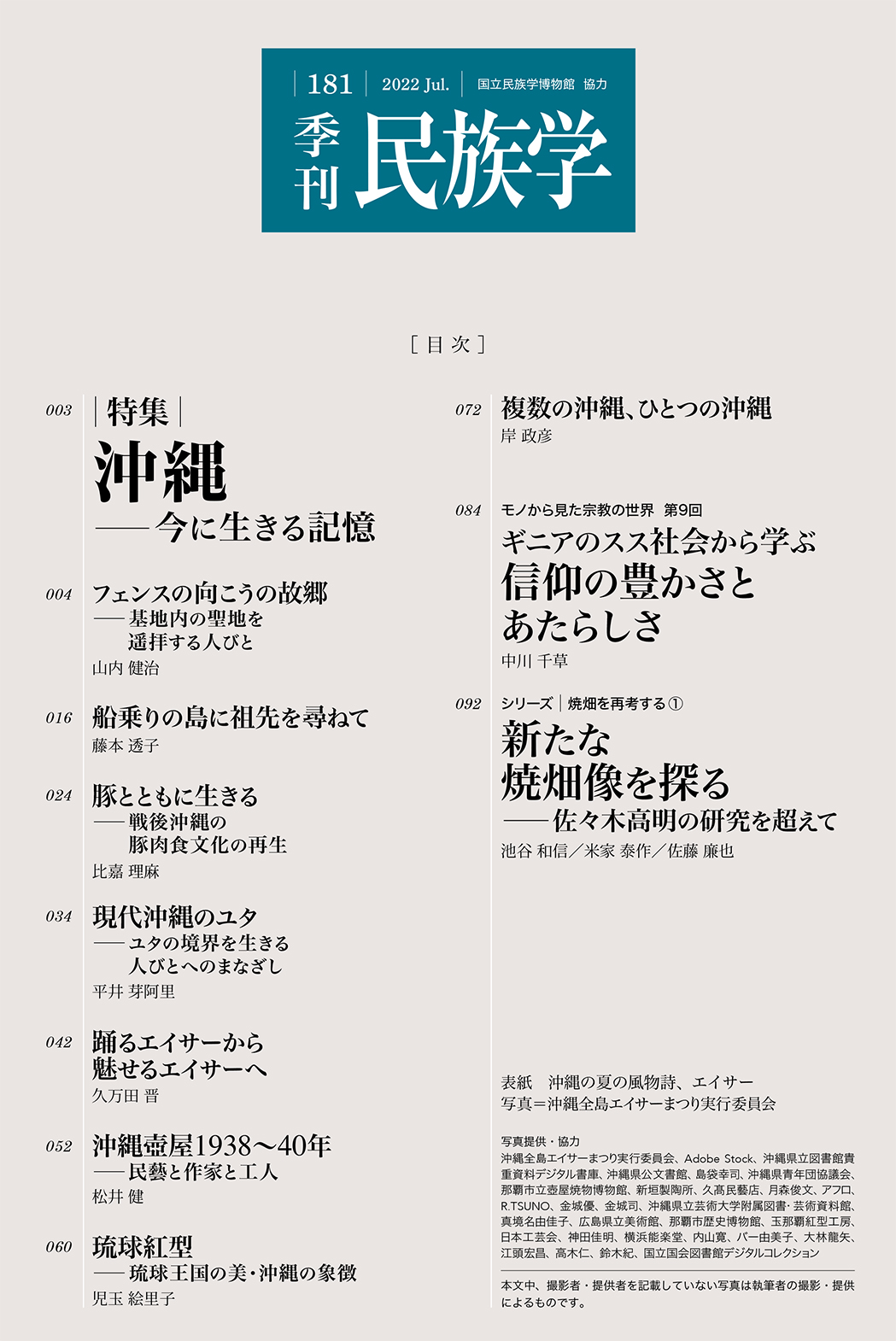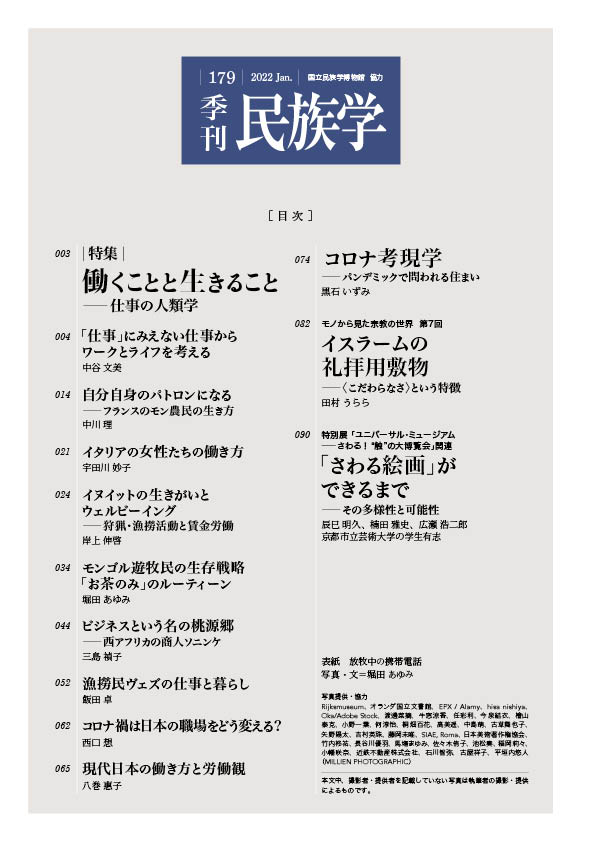特集 モンゴルの写真家インジナーシの世界
従来、アジアの国々は先進国の研究者や写真家によってまなざされ、写真記録が多く残されてきました。しかし現在、そうした国々でもみずからの社会の姿を鋭く切り取り発信する写真家たちが出てきています。本特集は、そのような一人、モンゴル気鋭の写真家 B. インジナーシ氏の作品を紹介しながら、従来の人類学者や写真家が撮影したモンゴル像と何が異なるのかを考察していきます。
今号でウクライナの歴史と文化を解説しておられる伊東一郎氏、若い頃民博におられた氏の澄んだテノールを懐かしく思い出します。複雑で難解なウクライナ史解説によって得心したのが、黒海へのアクセスの有無。大西洋にもつながるルートがロシアの欲望の源か、と近年よく耳にする「地政学」が少しわかった気がします。
地続きの大陸では、国境線がひんぱんに移動し、政治に翻弄されてきた人びとの苦労と、それに立ち向かうたくましさは、島国日本人には想像もおよびません。小松左京の『日本沈没』(光文社、一九七三年)は、海に守られひ弱な日本人が大陸に放りだされたらどうなるか、という思考実験を始めたところで終わってしまいましたが。
今号の特集は、今春の特別展の振り返り。撮る者、撮られる者、見る者、の三角関係を生み出す写真について、撮影者、主催者、鑑賞者が写真展を再考し、それを読者がともに考える、という構図は、写真を多く掲載する『季刊民族学』にまさにうってつけ、と自賛した次第。
この写真展のテーマのひとつは他者表象。メディア論が繰り返し語ってきたように、カメラのまなざしは撮る者と撮られる者との関係を確実に暴露すること、そして、植民地が拡大した一九世紀以降、いわゆる「旅行写真家」たちの写真などが、異文化に対して西欧の抱くイメージを増幅するのに加担してきたことを、この写真展でも再確認できました。
それに対し自己表象の旗手インジナーシ氏の写真は、見る者に「社会の矛盾を伝え、少数者の声を伝える」のが基本。矛盾の解決方法を示唆するのもまた、氏の生い立ちで培われた、温かいまなざしに他なりません。それが伝わるからこそ、氏の写真が共感をよぶのでしょう。
もうひとつのインジナーシ氏のテーマは、都市に集住するモンゴルの現実。ただ、都市に集住する人びとも、矛盾が高まり住みづらくなれば気楽にすみかを替える柔軟さをもっているのでは、とも思います。遊牧文化が根っこにあるモンゴルの人びとには、土地に固着しようとする日本人にはない、豊かな発想があるのではないでしょうか。それはウクライナ問題とも、重なってみえます。
(編集長 久保正敏)
2022(令和四)年10月31日発行
発行所:公益財団法人 千里文化財団
「国立民族学博物館友の会」へご入会いただければ定期的にお届けいたします。