2月の第3木曜日は「人類学の日」です。今年は本日、2月17日がその日となります。アメリカではじまり、世界各地で祝われるようになりました。しかし、日本ではなじみの薄い日であり、かく言うわたしも昨日までは寡聞にして知りませんでした。イェール大学に本部があり民博も加盟しているHRAF(Human Relations Area Files)からの情報に接し、さっそくネットであれこれ検索したところ、およそ次のようなことがわかました。
 「人類学の日」は文字どおりAnthropology Dayですが、略してAnthroDayとも称しています。アメリカ人類学会(American Anthropological Association、AAA)が2015年にNational Anthropology Dayとして定めましたが、たちまちWorld/International Anthropology Dayとよぶにふさわしい日となりました。趣旨は「人類学者がおのれの学問を祝い、周囲の世界と共有すること」にあり、大学や職場、コミュニティーなどでイベントを開催し、人類学が何であり、何ができるかをともに考えることにあります。なぜ2月の第3木曜日が選ばれたかというと、幼稚園から大学まで学期中であり、生徒や学生が参加できるからのようです。ただし、HRAFのように今年は2月28日(月)に祝うところもあり、日にち設定には柔軟性があるようです。
「人類学の日」は文字どおりAnthropology Dayですが、略してAnthroDayとも称しています。アメリカ人類学会(American Anthropological Association、AAA)が2015年にNational Anthropology Dayとして定めましたが、たちまちWorld/International Anthropology Dayとよぶにふさわしい日となりました。趣旨は「人類学者がおのれの学問を祝い、周囲の世界と共有すること」にあり、大学や職場、コミュニティーなどでイベントを開催し、人類学が何であり、何ができるかをともに考えることにあります。なぜ2月の第3木曜日が選ばれたかというと、幼稚園から大学まで学期中であり、生徒や学生が参加できるからのようです。ただし、HRAFのように今年は2月28日(月)に祝うところもあり、日にち設定には柔軟性があるようです。
本家のAAAは貸出用のアウトリーチ教材を用意していて、教室やミュージアムなどでの活用を後押ししています。他方、大学やミュージアムでは講演会やワークショップなどが開催され、展示もおこなわれています。2017年にはアメリカ以外にも12ヵ国(バングラデシュ、カメルーン、カナダ、エクアドル、エジプト、グアテマラ、インド、イタリア、メキシコ、パキスタン、タイ、トルコ)が参加し、2021年には15ヵ国、244の団体に増えたそうです。もっともコロナ禍にあって、ヴァーチャルな体験が中心となったのはやむをえないことでした。
たとえばイタリアのミラノでは昨年は3日間にわたって3000人の参加者を集め、新しいメディアや気候変動などのテーマで約40の会議やワークショップが開催されました。世界各地の大学やミュージアムでも創意工夫を凝らしたヴァーチャル体験―「場違いなミイラのミステリー」など―がとくに人気を博したとのことです。また、人類学の日にあわせてFacebook、Twitter、Instagramをつかった交流も盛んにおこなわれていて、その件数が表示されていました。
ところで、「人類学の日」はたんなる21世紀の産物ではありません。実は20世紀の初頭にも「人類学の日」と称される国際的なイベントがありました。1904年のセントルイス世界博覧会の期間中におこなわれた第3回オリンピック大会では、その一部として、博覧会の展示などにかかわっていた先住民たちの競技大会として実施されました。そこには4名のアイヌ男性も参加し、アーチェリーや槍投げで好成績を残しました。本稿の主題とは異なるので深入りはしませんが、もうひとつの「人類学の日」があったことだけは指摘しておきたいと思います。
ともあれ、今日の「人類学の日」は人類学という学問の重要性と必要性を人類学のサークルのなかだけでなく、広くまわりの人たちと分かち合う機会としてもうけられました。当財団においても、今後何ができるか、いろいろ知恵を絞っていきたいと考えています。(2022年2月17日)
 本展は、令和元年に国立民族学博物館(みんぱく)で開催され、好評を博した特別展「驚異と怪異」の一部を巡回するものです。近世以前、ヨーロッパや中東においては、人魚や一角獣といった不可思議だが実在するかもしれない生物や現象が「驚異」として自然誌の知識の一部とされてきました。また、東アジアにおいては、奇怪な現象や異様な生物の説明として「怪異」という概念が作り上げられてきました。高知展では、みんぱくの資料を中心に独自借用の資料も加え、龍、怪鳥、巨人など世界各地の人びとが創り出してきた不思議な生きものたちを紹介して、人間の想像力の面白さに迫ります。
本展は、令和元年に国立民族学博物館(みんぱく)で開催され、好評を博した特別展「驚異と怪異」の一部を巡回するものです。近世以前、ヨーロッパや中東においては、人魚や一角獣といった不可思議だが実在するかもしれない生物や現象が「驚異」として自然誌の知識の一部とされてきました。また、東アジアにおいては、奇怪な現象や異様な生物の説明として「怪異」という概念が作り上げられてきました。高知展では、みんぱくの資料を中心に独自借用の資料も加え、龍、怪鳥、巨人など世界各地の人びとが創り出してきた不思議な生きものたちを紹介して、人間の想像力の面白さに迫ります。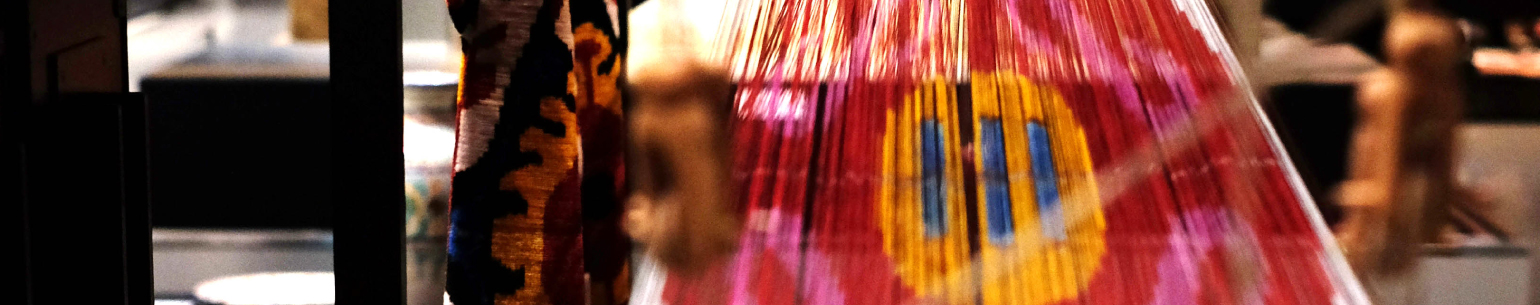
 「人類学の日」は文字どおりAnthropology Dayですが、略してAnthroDayとも称しています。アメリカ人類学会(American Anthropological Association、AAA)が2015年にNational Anthropology Dayとして定めましたが、たちまちWorld/International Anthropology Dayとよぶにふさわしい日となりました。趣旨は「人類学者がおのれの学問を祝い、周囲の世界と共有すること」にあり、大学や職場、コミュニティーなどでイベントを開催し、人類学が何であり、何ができるかをともに考えることにあります。なぜ2月の第3木曜日が選ばれたかというと、幼稚園から大学まで学期中であり、生徒や学生が参加できるからのようです。ただし、HRAFのように今年は2月28日(月)に祝うところもあり、日にち設定には柔軟性があるようです。
「人類学の日」は文字どおりAnthropology Dayですが、略してAnthroDayとも称しています。アメリカ人類学会(American Anthropological Association、AAA)が2015年にNational Anthropology Dayとして定めましたが、たちまちWorld/International Anthropology Dayとよぶにふさわしい日となりました。趣旨は「人類学者がおのれの学問を祝い、周囲の世界と共有すること」にあり、大学や職場、コミュニティーなどでイベントを開催し、人類学が何であり、何ができるかをともに考えることにあります。なぜ2月の第3木曜日が選ばれたかというと、幼稚園から大学まで学期中であり、生徒や学生が参加できるからのようです。ただし、HRAFのように今年は2月28日(月)に祝うところもあり、日にち設定には柔軟性があるようです。