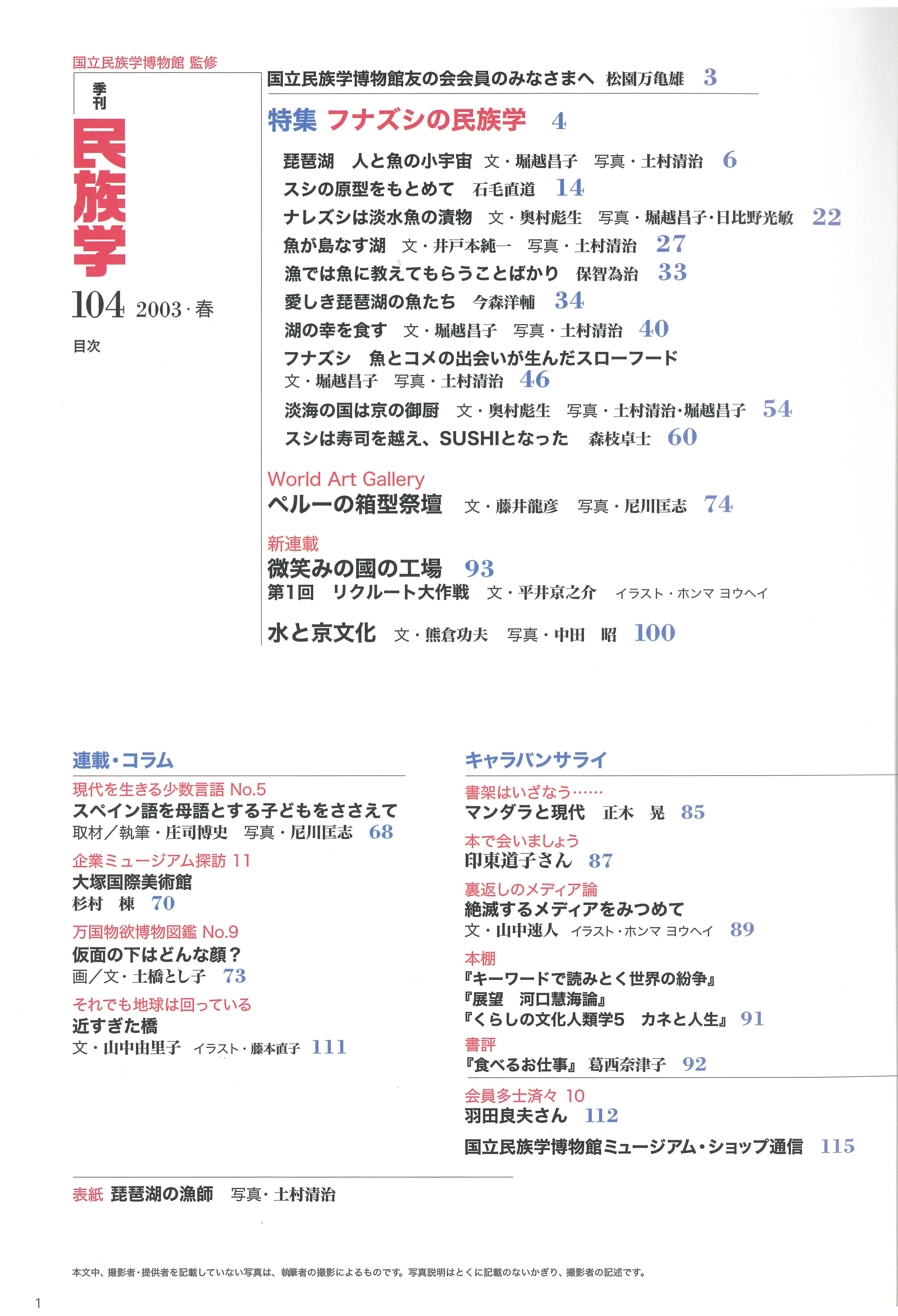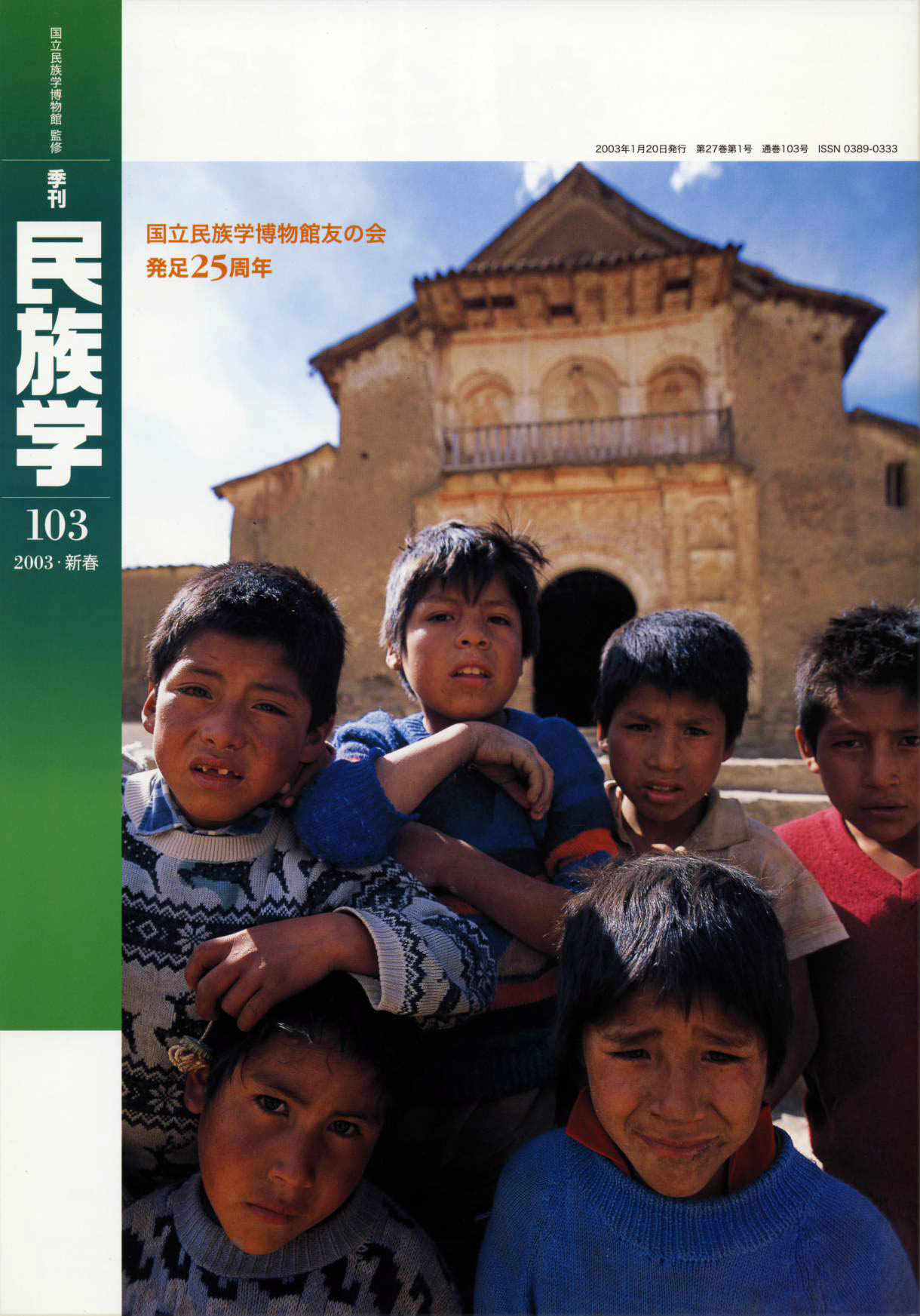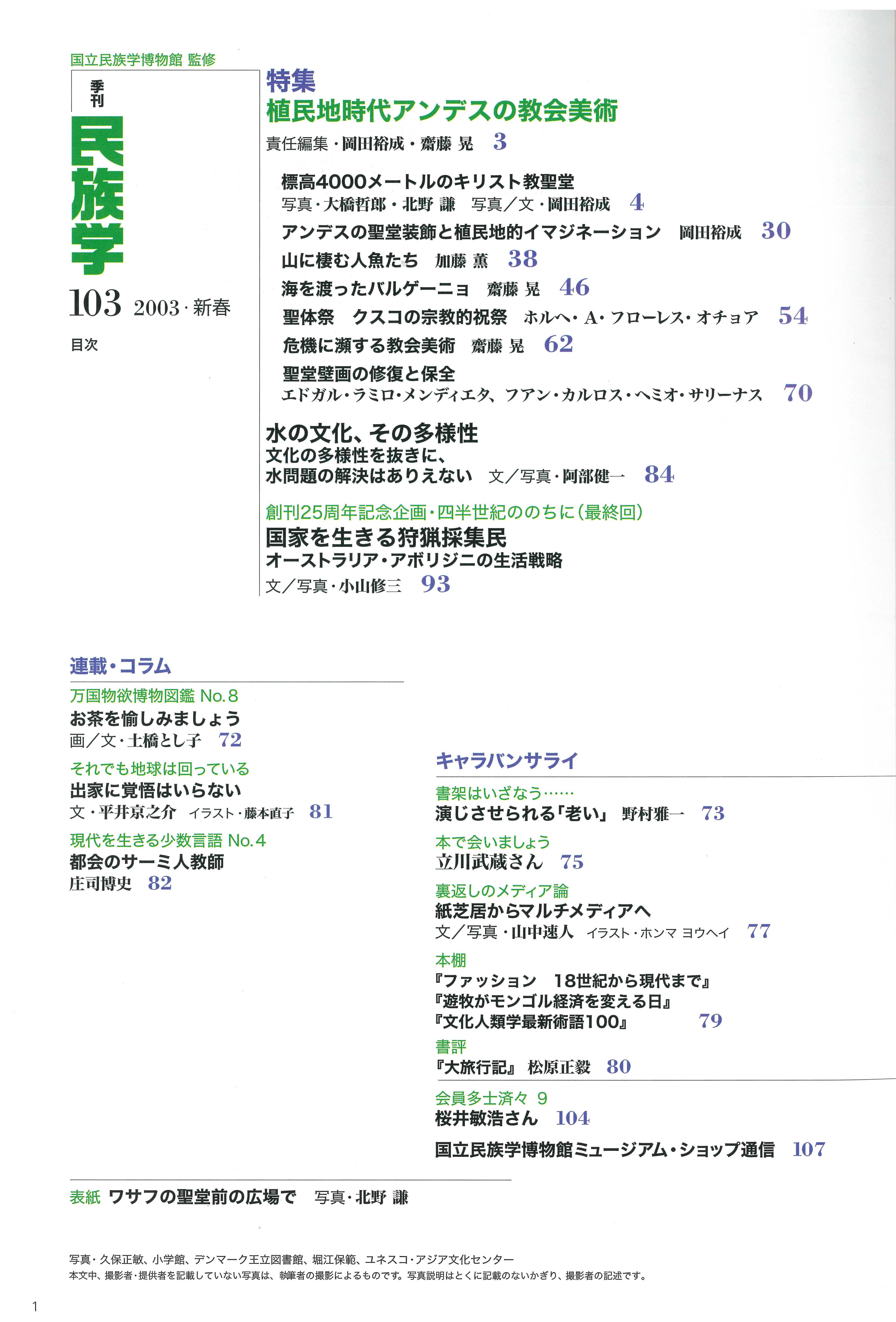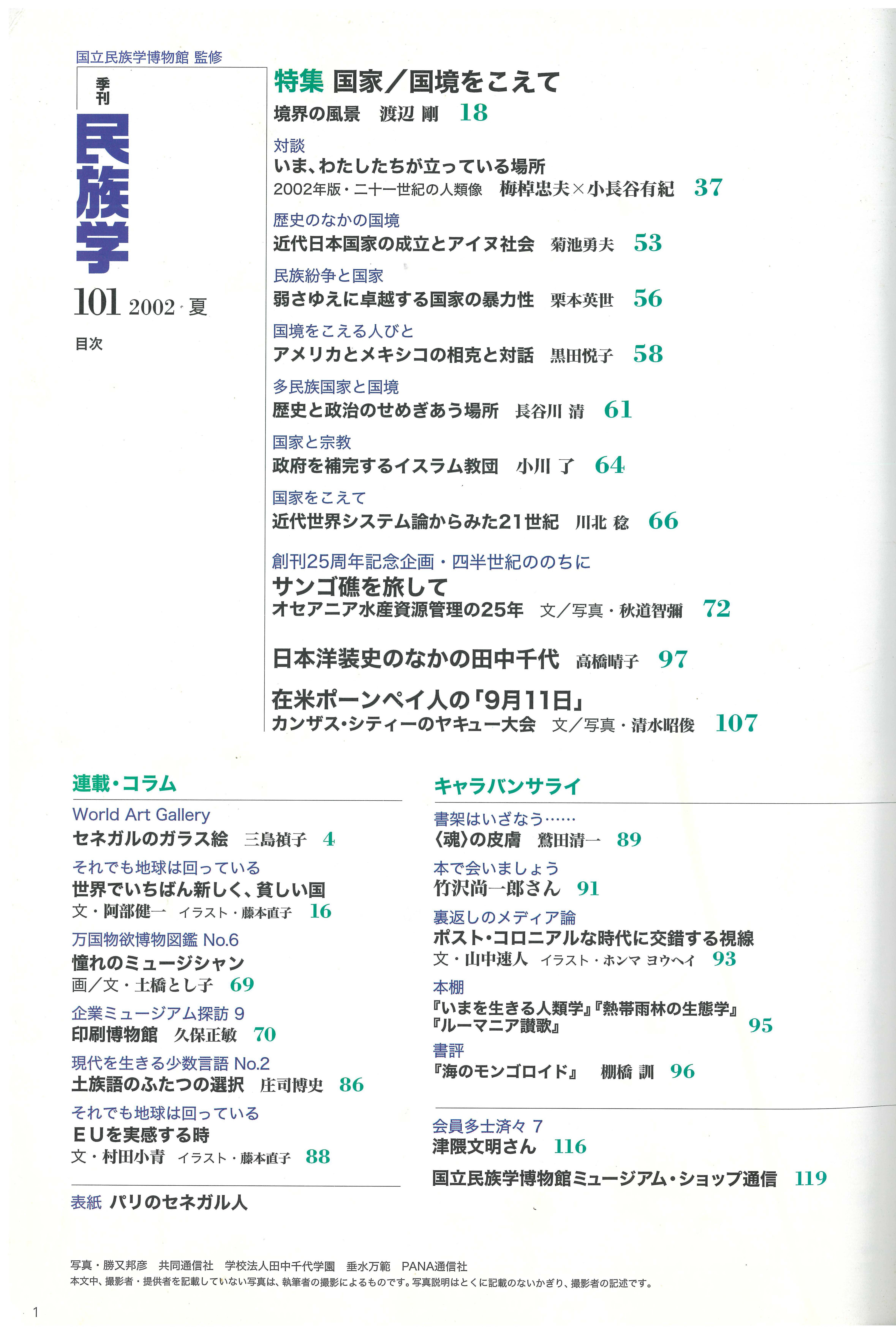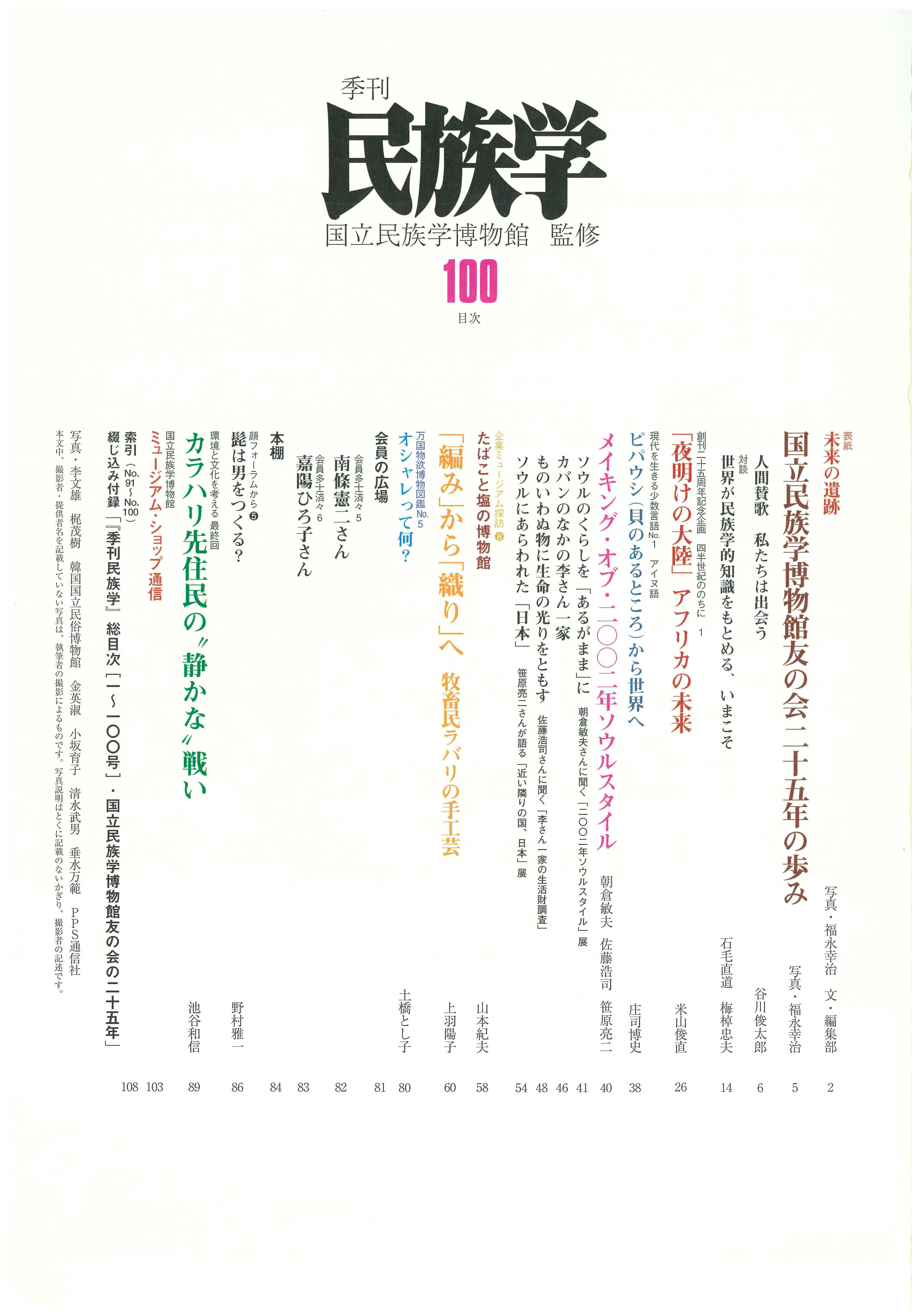特集 フナズシの民族学
琵琶湖特産のフナズシ。水田稲作の伝来とともに日本にはいってきた淡水魚の保存食が、そのまま現代まで受け継がれた希有な例だ。その起源は、さらに東南アジア大陸部にさかのぼるという。フナズシはたんなる伝統食品ではない。人類の食の営みの奥深さを示唆すると同時に、人間に環境との新たな関係をせまる象徴的な意味合いも帯びはじめた。フナズシの問いかけに耳をすませたい。
琵琶湖 人と魚の小宇宙 文・堀越 昌子/写真・土村 清治
琵琶湖のまわりに人間が住みはじめたのは、数万年前のことだ。縄文時代には。さかんに漁撈活動がおこなわれていたことが知られている。深く長い湖と人間のかかわりを、もういちど見つめ直したい
スシの原型をもとめて 石毛 直道
日本食の代表として世界に知られている「スシ」は、すでに各国で独自の形に変化しつつある。われわれがいま食べているスシも、何度かの変遷を経たものだ。保存食から即席料理へとその性格も変化した「スシ」の歴史をたどる
ナレズシは淡水魚の漬物 文・奥村 彪生/写真・堀越 昌子、日野 光敏
東南アジアの平野部で生まれた淡水魚の保存技術は、稲作とともに海をわたり日本へとつたられた。やがて国内各地でその地の産物をとりいれて、ナレズシの多彩なバリエーションが展開する
魚が島なす湖 文・井戸本 純一/写真・土村 清治
フナズシには、琵琶湖やそこにすむ魚たち、周辺の陸地やそこに人びとが築きあげてきた「共働」の長い歴史が刻まれている。湖の再生は、いちど分断されたこれらの共働をふたたび取りもどせるか否かにかかっている
漁では魚に教えてもらうことばかり 保智 為治
愛しき琵琶湖の魚たち 今森 洋輔
机での作業に区切りがつくと、すぐに筆を置き野外に出掛けていく。春先の漁港に吹き込む風は、水草の青い匂いと魚の匂いが混ざりあって独特の香りがする。それは琵琶湖特有の匂いだ。琵琶湖はきょうも青く美しい。けれども…
湖の幸を食す 文・堀越 昌子/写真・土村 清治
人びとの琵琶湖と湖魚への思い入れは深く、湖魚料理の種類もおおい。滋賀県は琵琶湖のおかげで、日本でもっとも淡水魚利用が発達した地域といえる
フナズシ 魚とコメの出会いが生んだスローフード 文・堀越 昌子/写真・土村 清治
子どものころから、お腹をこわしたり風邪をひいたとき、また正月や祭りの日にも食べてきたフナズシは、滋賀の人びとにとってふるさとの特別な味である。しかも、頭から尾っぽまで丸ごと食べられ、消化しやすく、整腸作用と高い抗菌力をもつ完全食品でもある
淡海の国は今日の御厨 文・奥村 彪生/写真・土村 清治、堀越 昌子
近江地方は古くから食の宝庫であった。琵琶湖や川で獲れる淡水魚のみならず、平野部や山里からも四季折々に、ゆたかな実りと収穫がよろこびをもたらした。鯖街道を運ばれる海産物も加わり、それらは京の都で洗練された味覚へと生まれかわる
スシは寿司を越え、SUSHIとなった 森枝 卓士
オーストラリアの片田舎、南アフリカのケープタウン、チリのサンチャゴにむかう飛行機のなか…、いまや世界のいたるところで出会うスシ。しかしそれはすでに寿司ではなく、土地土地で変容をとげた、インターナショナルな食べものとしてのSUSHIだった
第三回世界水フォーラムによせて
水と京文化
文・熊倉 功夫/写真・中田 昭
京都の名物といえば水。第一は鴨川、桂川、宇治川などで知られる川の水。第二は東山の山すそのいたるところから湧きでる湧水。これら京の名水からゆたかな京文化が生まれ、今日まで脈々とはぐぐまれてきた