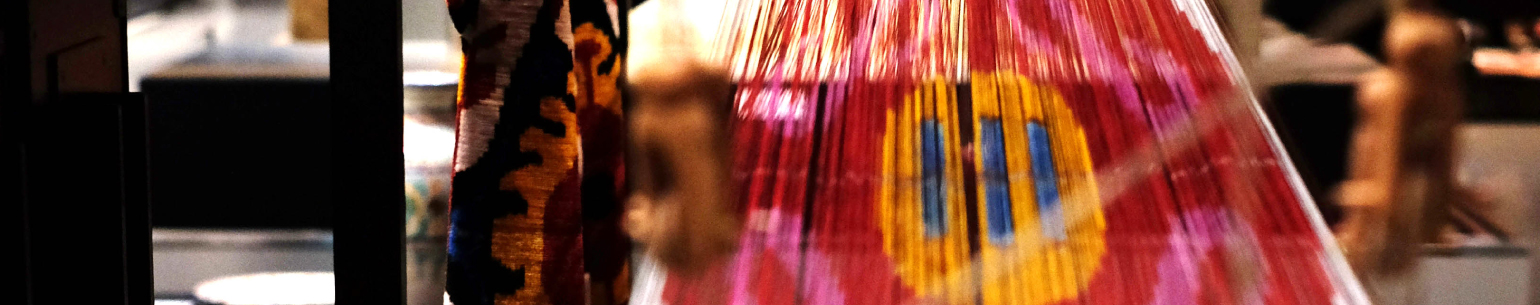われわれ現代人は、各種メディアが加工した情報にならされ、自身で思考せず安易に答えや結果を求め、わかったような気になってすます傾向があるように思います。しかし、近頃、世の中は大きく変わりはじめてきているように感じますが、その変化に対応するには、これまでのやり方を少し変えてみる必要もあるのではないでしょうか。思考を鍛えるのは非常に骨の折れることですが、自分で考えて、その考えを人に話し、反対に人の考えを聞き、その上でさらに考えるということを真剣にはじめてみませんか。 「かんがえるための講座」は、これまでじっくり思考を鍛え上げてきた人の上質の話しをじっくりと聞き、じっくりともに考え、自分自身で思考することを鍛えるための場所です。今回のシリーズでは、異文化理解について、イスラームを題材に考えます。
20世紀、21世紀にわたって、中東紛争は大きな国際問題であり、中東だけでなく世界各地で、イスラームを掲げた戦闘的な政治活動(テロリズム)が生じています。そのため、イスラームは世界秩序にとって「大きな脅威」「危険な宗教」という見方も強まっています。しかしながら、世界に13億も信者がいるといわれる宗教が、本当に危険で脅威なのでしょうか。世界の総人口の2割をこえる人々が「野蛮なテロリスト」なのでしょうか。こういう時代だからこそ、イスラームを理解することは、重要な課題です。
そこで、講師に、日本におけるイスラーム研究の専門家で、異文化理解について長年、熟考なさってきた社会人類学者、大塚和夫先生を迎え、「テロ」に還元できないイスラームのあり方を紹介していただき、それとともに日本においてイスラームという異文化を理解するためのいくつかの要点をお話ししていただきます。
第1回 8月2日(木) アッラーは“神”と訳しうるか ― 教義について
第2回 8月3日(金) イスラーム社会はどのように秩序づけられているのか ─ イスラーム法について
第3回 8月6日(月) ムスリムはどのような宗教生活を送っているのか ─ 儀礼・祭礼について
第4回 8月7日(火) イスラームは現代世界の脅威なのか ─ イスラーム復興について
※時間はいずれも13:30~16:30