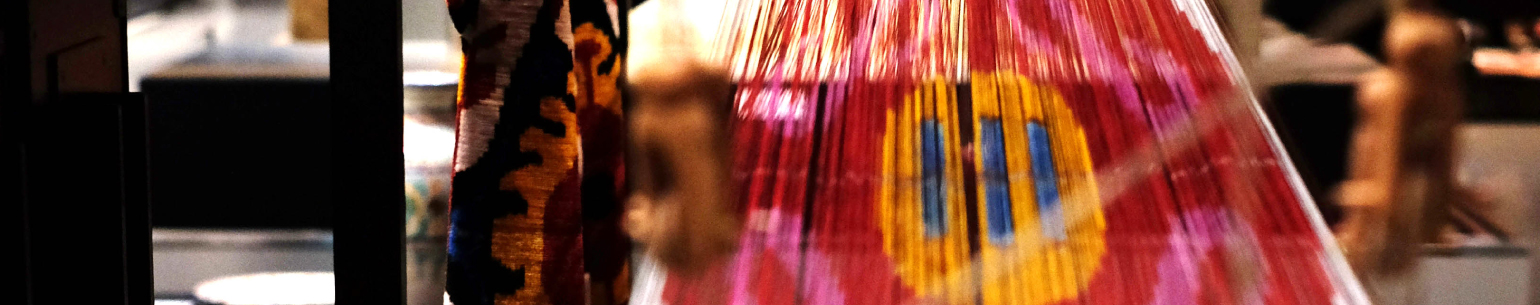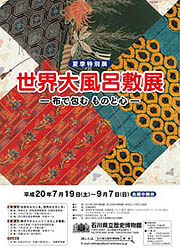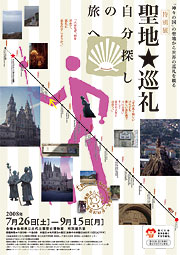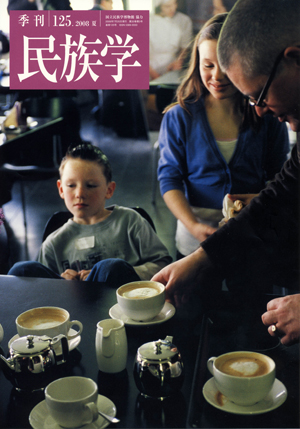長崎県美術館 企画展「世界大風呂敷展」(終了)
石川県立歴史博物館 夏季特別展「世界大風呂敷展」(終了)
島根県立古代出雲歴史博物館 特別展「聖地★巡礼」(終了)
「世界大風呂敷展」では、世界24カ国から蒐集した色鮮やかな包み布や日本の伝統的な染めや刺繍の技法でつくられた風呂敷、また、地元加賀地方の風呂敷など、約150点を展示します。この展覧会は、2002年秋の民博での開催以来、これまで日本各地を巡回してきました。1月27日から長崎県美術館で開催。環境保護や日本の伝統文化の継承などで、近年、注目をあびている風呂敷の世界をお楽しみください。
「聖地★巡礼」展は、昨春(2007年)、民博特別展として開催されたばかりの展覧会です。本展覧会では、ローマ、エルサレムと並ぶキリスト教三大聖地のひとつサンチャゴ・デ・コンポステラへの巡礼をはじめ、奇跡の泉として有名なルルド、さらに四国お遍路さんや恐山といった日本の聖地巡礼などの映像を中心に紹介します。今回は民博開催時の資料に新たな資料を追加し、日本最古の聖地のひとつ“出雲”において、より身近なものとしての「聖地」、「巡礼」について考えていただければと思います。
長崎県美術館
企画展 「世界大風呂敷展 ─ 布で包むものと心 ─」
会期
2009年1月27日(火)~3月22日(日) 〈休館日:2/9(月)、2/23(月)、3/9(月)〉
開館時間
午前9時~午後8 (入館は午後7時30分まで)
会場
長崎県美術館 企画展示室
入館料
一般 900円(800円)
大学生・70歳以上600円(500円)
高校生 400円(300円)、
中学生以下
無料 ※( )は前売および20名以上の団体料金 「国立民族学博物館友の会」会員は団体料金で入館できます。
主催
長崎県美術館
KTNテレビ長崎
国立民族学博物館
財団法人千里文化財団
特別協力
宮井株式会社
協力
裏千家長崎支部 長崎雑貨たてまつる
後援
長崎県 長崎県教育委員会 長崎市教育委員会 長崎県立長崎図書館 長崎市立図書館 日本きもの連盟長崎支部 長崎新聞社 西日本新聞社 朝日新聞社 毎日新聞社 読売新聞長崎支局 NHK長崎放送局 長崎ケーブルメディア エフエム長崎
助成
独立行政法人日本万国博覧会記念機構
協賛
ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート
石川県立歴史博物館
夏季特別展 「世界大風呂敷展 ─ 布で包むものと心 ─」
会期
2008年7月19日(土)~9月7日(日) 〈会期中無休〉
開館時間
午前9時~午後5時 (入館は午後4時30分まで)
会場
石川県立歴史博物館 特別展示室
入館料
一 般 700円(560円)
大学生 550円(440円)
高校生以下 無料
※( )は20名以上の団体料金 「国立民族学博物館友の会」会員は団体料金で入館できます。
主催
石川県立歴史博物館
国立民族学博物館
財団法人千里文化財団
共催
北國新聞社
特別協力
宮井株式会社 ゑり華
助成
独立行政法人日本万国博覧会記念機構
後援 NHK金沢放送局 北陸放送 テレビ金沢 金沢ケーブルテレビネット エフエム石川 ラジオかなざわ ラジオこまつ ラジオななお
島根県立古代出雲歴史博物館
特別展 「聖地★巡礼 ─ 自分探しの旅へ ─」
会期
2008年7月26日(土)~9月15日(月・祝) 〈会期中の休館日は8月19日(火)〉
会場
島根県立古代出雲歴史博物館 特別展示室
観覧料
一 般 1,000円(800円)
大学生 500円(400円)
小中高生 300円(240円)
※( )は20名以上の団体料金
主催
島根県立古代出雲歴史博物館
国立民族学博物館
財団法人千里文化財団
財団法人自治総合センター
助成
独立行政法人日本万国博覧会記念機構
後援
出雲国「社寺縁座の会」 朝日新聞松江総局 毎日新聞松江支局 読売新聞松江支局 産經新聞松江支局 日本経済新聞社松江支局 中国新聞社 山陰中央新報社 新日本海新聞社 島根日日新聞社 NHK松江放送局 BSS山陰放送 日本海テレビ 山陰中央テレビ エフエム山陰 山陰ケーブルビジョン株式会社 出雲ケーブルビジョン株式会社 ひらたCATV株式会社
協賛
パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社
協力
株式会社志摩スペイン村
*本事業は日本万国博覧会記念基金の助成をえて実施いたします。